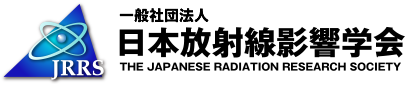Wee1とATRの阻害は腫瘍特異的な合成致死を引き起こし、転移を抑制する
| 論文標題 | Inhibiting Wee1 and ATR kinases produces tumor-selective synthetic lethality and suppresses metastasis |
|---|---|
| 著者 | Bukhari AB, Lewis CW, Pearce JJ, Luong D, Chan GK, Gamper AM |
| 雑誌名・巻・ ページ・発行年 |
J Clin Invest., 129(3):1329-1344, 2019 |
| キーワード | 合成致死 , Wee1 , ATR , DNA損傷 , 複製ストレス |
【背景・目的】
癌細胞では、DNA損傷や複製ストレスなどの様々なストレスによるゲノムの損傷が脅威となる。また、癌細胞はDNA損傷応答が破綻していることがしばしばみられるため、ゲノムの損傷がその細胞にとってどのようなレベルであるかはDNA損傷応答がどの程度うまく働くかに依存する。合成致死(synthetic lethality)とは、BRCA遺伝子に変異を有するために相同組換えが正常でない乳がん細胞においてPARP阻害剤が奏功することに示されるように、1つの遺伝子摂動では致死性を示さないが、2つの遺伝子摂動が同時に存在するときに細胞死に至ることを指す。しかし、この効果はある遺伝子背景や環境に限定して発揮されるに過ぎないため、著者らは、正常細胞にはみられず癌細胞特異的に共通してみられる状態を同定することが合成致死を引き起こす上でより重要であると考えた。癌細胞は正常細胞と比較し、DNA損傷や分裂ストレス、複製ストレスが高い状態となることが知られているため、治療においては遺伝毒性を与えることに加え、DNA損傷応答経路を同時に阻害することで、癌細胞特異的に細胞死を誘導できるのではないかと推測し、これらに関わるWee1とATRに着目した。Wee1は、M期への進入や終了を調整するのみならず、DNA複製にも重要な役割を担っており、Wee1を阻害するとS期でDNA損傷が出現することが報告されている。一方、ATRは放射線などによるDSB応答において必要不可欠であり、S、G2/M期チェックポイントの活性化や相同組換えに重要であることがよく知られている。現在、Wee1阻害剤(AZD1775)とATR阻害剤(AZD6738)は放射線治療や化学療法と併用でのphase I/IIの臨床試験が行われているものの、その両阻害剤の併用効果についての報告はほとんどないため、著者らはin vitro、 in vivo両面からその検討をおこなった。
【結果】
Wee1阻害剤処理により、ATRが活性化し、さらにATR阻害剤を併用することで8種のがん細胞において相乗的に生存率が減少した。一方、正常細胞では併用効果を認めなかった。また、ATRの下流のChk1の阻害剤は、単剤もしくはWee1阻害剤との併用で正常細胞に極めて感受性であり、このことは、Chk1阻害剤は正常細胞にもDNA損傷を引き起こすこと、Phase Iの臨床試験で毒性が報告されていることとも一致した。Wee1阻害剤やATR阻害剤のように癌細胞においてのみ奏功することが、治療に応用する上で重要である。
次に、細胞動態を調べるためにヒストンH2Bとチューブリンを蛍光標識した乳がん細胞に阻害剤処理をした結果、Wee1阻害剤単剤もしくは併用においてのみM期(核膜崩壊~anaphase)が延長し、M期の長さとM期中での細胞死の割合は相関しているようであった。単剤、併用ともに細胞死は、M期中、mitotic slippage後やcytokinesis後の間期でみられ、大部分がM期に入った後に起こることから、M期での異常が娘細胞の細胞死につながるものと考えられた。細胞を同調させ、細胞周期別の生存率を調べると、単剤では、late G1~M期処理では有意に生存率が低下したが、より短時間の処理では効果が得られなかった。一方、阻害剤併用では、S期のみもしくはlate G2~M期の短時間処理でも生存率は約50%まで低下、late G1~M期では10%以下まで低下し著明な効果を認めた。また、G1期の細胞に阻害剤処理をすると、併用でDNA量2N~4Nの細胞が増加し、その分画はその後も存在し続けた。併用時は動原体の断片化が多くみられたことからも、複製が正常に完了しないまま細胞がM期へと進行していることが推測された。すなわち、S、G2/M期における阻害剤の作用がmitotic catastropheを引き起こすことが、相乗効果を生むものと示唆された。
次に、乳がん細胞をNSGマウスに同所性に移植し、40-50 mm3まで増大した時点から阻害剤を5日以上投与した後の標本を観察すると、併用群でγH2AXの発現は増加、増殖期の細胞は減少し、アポトーシス細胞は有意に増加しており、相乗効果を示した。また、副作用を調べるため、腫瘍を形成した免疫応答(NSG)マウスと免疫不全(C57BL/6)マウスに、阻害剤を26日間投与したが、単剤、併用群いずれにおいても明らかな体重・摂食状態変化、炎症所見や脾臓サイズの変化もみられなかった。薬剤によって特に損傷を受けやすいとされる腸幹細胞においても、26日までにほぼ変化はみられなかった。C57BL/6マウスから摘出した骨髄のFACS解析でも、単剤、併用群いずれにおいても造血幹細胞などの減少はみられなかった。さらに、治療終了の26日目の標本におけるγH2AX発現は、肺、肝臓、腎臓では検出されず、回腸や脾臓ではWee1阻害剤単剤または併用で増加したものの、37日目には元のレベルに戻っていた。このことから、活発に増殖している正常細胞よりも癌細胞の方が、DNA損傷が増加していることが明らかとなった。
治療効果は、単剤群では治療終了後に急速な再増殖がみられたが、併用群では9匹中6匹のNSGマウスでCR(完全奏功)が得られ、著明な抗腫瘍効果を認めた。治療開始後の生存日数の中央値は、ATR阻害剤群が60日、Wee1阻害剤群が62日、併用群が103日、対照群が53日であり、併用により、癌特異的な合成致死を起こしたと考えられた。また、腫瘍のルシフェラーゼ活性測定により、併用では遠隔転移が減少していることが確認できた。治療開始を、250 mm3と微小転移が既に生じているであろう時期にすると、単剤群では増殖遅延のみであったが、併用群では腫瘍の縮小がみられた。また併用群のみで、胸部リンパ節転移がなかった。摘出標本においてルシフェラーゼ活性で微小転移を検出した結果、対照群や単剤群ではリンパ節、肺、肝臓、骨などへの転移がみられたが、併用群では微小転移も認められなかった。
最後に、使用した乳がん細胞のMDA-MB-231は高浸潤能を有するにもかかわらず、阻害剤の併用で転移を抑制したことから、癌幹細胞への作用を検討した。2種の乳がん細胞株から癌幹細胞に富む分画(SP)とそうでない分画(NSP)を単離し阻害剤への感受性を調べたところ、SP分画はNSP分画と比較し、阻害剤単剤には抵抗性であったが、驚くべきことに、阻害剤併用では両分画は同等の感受性、すなわち、癌幹細胞に対しての方が、その他の癌細胞よりも併用による相乗効果が高いといえ、このような報告は初めてである。このことから、単剤では癌幹細胞に抵抗性であったものが、併用により相乗効果を示すことで、高い転移抑制効果を発揮していたものと考えられた。
【まとめ】
著者らは、癌細胞特異的なDNA損傷の生じやすさに着目し、Wee1阻害剤とATR阻害剤を併用することで合成致死が得られ、抗腫瘍効果を示すことを明らかにした。また、癌幹細胞に対し、阻害剤単剤では抵抗性であったが、併用により相乗的に感受性となるという新たな知見は、早期の臨床応用につながることが期待される。